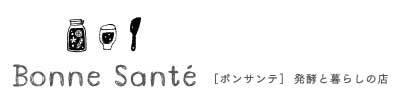ゆずはミカン科ミカン属の果実です。原産地は中国ですが、日本でも古くから栽培されています。果汁はもちろん、鮮やかな黄色の果皮に特有の香りがあり、日本料理では薬味や調味料として用いられます。
ゆずの歴史
ゆずの原産地は中国の揚子江上流といわれています。
日本へは飛鳥から奈良時代に朝鮮を経て伝わったと考えられており、初めは薬として用いられていたようです。
その後日本全域で栽培されるようになり、昭和40年代までは埼玉県が主な産地でしたが、現在では四国地方の高知県、徳島県、愛媛県の3県で多く栽培されており、国産ゆずの約8割を占めています。
ゆずの香り成分とその効果
・ユズノン
ユズノンはゆずの黄色い皮の部分に含まれる香気成分です。
ゆず特有の香りはユズノンによるものですが、ごくわずかな量しか含まれていません。
果皮の表面に見える小さな点(油胞)に多く含まれており、皮に傷をつけたり、皮をしぼるとゆずの香りが強くたちます。抗菌、殺虫、鎮痛作用などのほか、気分をリフレッシュしたり、集中力を高める効果やリラックス効果があります。血行を促進し、体を温める効果もあるといわれます。
・リモネン
リモネンは柑橘類には共通して含まれていますが、ゆずにはレモンよりも多くのリモネンが含まれています。
リモネンは交感神経の働きを活性化させ、脂肪の分解を促進して内臓脂肪を減少させる働きがあるといわれています。また食欲を抑える効果もあるといわれます。
リモネンは皮膚に触れるとピリピリと刺激を感じたり、かゆくなることがあります。
果皮に傷が入るとリモネンが流出するので、肌の弱い人は注意しましょう。
・シトラール
レモンなどの柑橘類に含まれる香りです。
シトラールには抗菌、鎮痛、鎮静作用があります。
また免疫力を維持する働きがあり、風邪の予防や、疲れたときにかかりやすい口唇ヘルペスなどを予防する効果があるといわれています。
ほかにも血行を促進したり、気分を落ち着かせる効果もあります。
ゆずに含まれる栄養
ゆずの栄養成分の多くは、果肉よりも果皮に多く含まれています。
果汁を利用するだけではなく、皮を食べることで効率よく栄養成分摂取できるといえます。
ヘスペリジン
ヘスペリジンは柑橘類に含まれているフラボノイドでポリフェノールの一種です。
ビタミンと似た働きをもち、ビタミンPと呼ばれることもあります。
マウスの実験では血圧を下げたりコレステロール値の上昇を抑える効果のほか、骨密度の低下を抑制する効果も認められています。他にも抗アレルギー作用やリウマチの症状改善など、さまざまな生理機能が期待されています。
ビタミンC
ビタミンCは抗酸化作用によって体内でおこるさまざまな酵素反応を助けています。体内で合成することができないため、食物から摂る必要があります。ビタミンCが不足することで皮膚のコラーゲンが減少したり、骨密度の低下などを引きおこす可能性があります。また免疫力をアップして風邪などの感染症を予防したり、鉄分の吸収を促進して貧血を予防するなど、幅広い健康効果をもつビタミンです。
ペクチン
ペクチンは水溶性食物繊維のひとつで植物には広く含まれており、植物の細胞と細胞をつなぐ接着剤のような役割をしています。整腸作用により下痢や便秘を予防・改善する効果があるほか、血中の悪玉コレステロールを下げ、動脈硬化の予防などにも効果が期待されています。
薬膳の効果
気の巡りを良くして胃の不快感を和らげたり、鎮咳や去痰の効果もあります。酔いをさます作用があるので、お酒を飲んだあとにもよいでしょう。漢方ではゆずの果汁は橙子(とうし)、果皮は橙子皮(とうしひ)、種は橙子核(とうしかく)という名前で生薬としても利用されています。