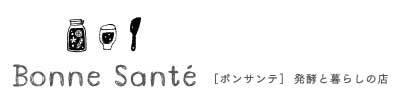「紫蘇」というのは中国での植物名であり、日本語で「シソ」と呼ぶのも、この中国での名前(漢名)
が由来になっているからです。
品種がとっても多い紫蘇の中で、食用にしていて、葉の色が赤いものを特に「赤紫蘇(赤シソ)」
と呼んでいます。
梅干しの色としてもなじみ深い、赤い色というのが一番の特徴ですね。
元はヒマラヤやミャンマー、中国南部が原産であり、日本にも中国から伝来したと言われています。
その伝来は遥か縄文時代に遡るんだとか。
ただ、本格的に栽培を始めたのは平安時代になってからとされています。
尚、赤紫蘇の旬は初夏で、需要は梅干しを漬ける時期に集中するので、例年6~7月中旬頃までしか出回りません。
見た目はただの葉っぱですが、含まれている栄養はたくさん!
ニンジンやピーマンといった緑黄色野菜に豊富に含まれているβカロテンが赤紫蘇にも含まれています。
これは体内でビタミンAに変換されて作用することから、皮膚や粘膜の健康を維持する働きが期待できるとされているんです。
また、強い抗酸化作用や防腐・殺菌にも作用があるとされているのです。お弁当に梅干を入れた「日の丸弁当」
は美味しさ以外にも、防腐作用という観点からも理にかなっています。
また、大きな特徴である赤い色が、色素成分のシアニジンとして含まれています。
聞き覚えのない成分ですが、これは色素成分「アントシアニン」のグループに含まれる成分です。
ブドウやブルーベリー、ラズベリーやスモモなど、赤色をした果物に含まれている成分です。
効能としては眼精疲労の軽減や、全身の疲労回復も効果
目のピント調整機能のサポートをして、その機能を改善させるとも。「ブルーベリーは目に良い」
とよく言われますが、それと同じ、ということですね。
そもそも赤紫蘇と青紫蘇の違いは何なのでしょうか?
元々の「紫蘇」という言葉に含まれている紫の文字の通り、元々の紫蘇は赤紫蘇を指していたようです。
赤紫蘇はアクが強く、そのままで食べても美味しくありません。
塩もみをしてアクを抜いた後で使うことが多いです。
梅干しやお漬物の色付けとして使われているのは皆さんもご存知の通り。
赤紫蘇は酸に触れると赤色がより鮮やかになることから、梅干を漬ける際には梅酢をほんの少し加えることで
よりキレイな赤色になります。